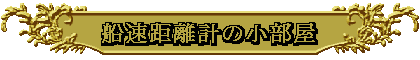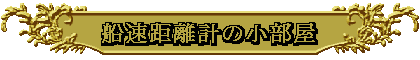船では、速力計を「ログ ( Log ) 」と言います。上の写真は「ドップラー・ソナー・ログ」
です。移動する物体から発射する音は、それが近づいて来るときは音が高くなり、遠ざかる時
は低くなります。例えば、救急車のサイレンの音は、近づいてくる時は高く聞こえ、通過した
瞬間から低く聞こえる様になりますが、この現象を「ドップラー効果」と言います。船底から
船首尾方向に発射され、海底や海水塊に反射されて戻って来た音波を受信し、発信音波と受信
音波の周波数の変化から速力を算出する装置が「ドップラー・ソナー・ログ」なのです。
ソナー(SONAR)とは、Sound Navigation and Ranging の略です。ソナーは、垂直ソナー
と水平ソナーに分けられます。垂直ソナーは音響測深機や魚群探知機とも言われる事がありま
すが、一般にソナーと言う時は後者の水平ソナーを指しています。ソナーは自船の全周囲又は
扇形角度範囲にわたって放射された超音波が目標物に当って返ってくる反射波を受信して、目
標物の方向と距離を測定するものです。潜水艦などには、欠かせない計器と思います。 |