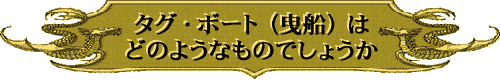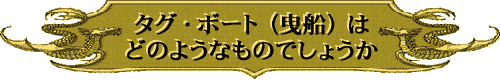当ホームページの管理者である私は、二等航海士時代の若い時分、昭和42〜43年の1年間、「あま
りりす」に乗船した経験があります。
「あまりりす」は昭和42年(1967年)の建造で、その処女航海が、カナダのバンクーバーから台湾
の高雄港までのカナダ海軍の退役フリゲート艦の曳航で、次がアメリカ南部、メキシコ州ヒュースト
ン河口ガルベストン湾のポート・アーサーからオーストラリア西岸のフリーマントルまでの海底油田
掘削装置の曳航。その次はフリーマントルで海底油田掘削装置を引渡した後、日本への帰途の途中、
本社からの緊急指令でインド洋西部、セイシェル諸島のビクトリアから釜石港までのスクラップを満
載して火災を起こして錨泊中のアメリカの総トン数2万トンの貨物船の曳航、などを経験しました。
これらの曳航で思い出深いものは、ポート・アーサーからフリーマントルまでの海底油田掘削装置
の曳航です。この掘削装置(ジュビリー 号)の大きさは、長さ 72M 幅 50M程もあり、4本の脚は
デッキ上の高さ約70M で、ポート・アーサー港外に錨泊している姿は凄く巨大に見えました。
ポート・アーサーからフリーマントルまでの距離は一万マイル以上あり燃料の最大保有量から直行
は不可能のため、燃料と食料の補給地としてブラジルのレシフェ港と南アフリカのケープタウン港の
2港に寄港することが決定され、昭和43年3月25日、ジュビリー 号を曳航してレシフェ港向け、ポー
ト・アーサーを出港しました。曳航索は800メートル2本を最大に延ばし、一万馬力のエンジンをフル
回転させるのですがスピードは4ノットしか出ません。予想では6ノット位は出るだろうとの事でし
たが掘削装置の脚が船底下に数メートル突出しているため、予想以上に海水抵抗が大きい様でした。
フロリダ半島を廻るときなどはメキシコ湾流が強く進路維持が困難なほどでした。また、バハマ諸
島沖からブラジル沿岸に沿って北に流れるアンチル海流や南赤道海流があり、約 4,200マイルを 42日
かかって 5月 6日、無事にレシフェ港に着きました。
レシフェ港からケープタウンまでの距離は約 3,300マイル。 30日程で到着する予定でしたが、ケー
プタウンに入港する前日から移動性低気圧に遭遇し、西風が次第に強まり、夜半には山の様な追い波
が船尾から襲いかかる状態となり、夜半過ぎ、船体に異様な振動を感じたと同時に速力計の示度が 13
ノットに急上昇し、曳航索が切断した事を知りました。被曳船“ジュビリー号”にはアメリカ人 20 名と
監視要員として副三等航海士が乗組んで居りましたが、本船が次第に視界から遠ざかるため副三等航
海士はVHFで本船を悲痛な声で呼び続けておりました。
本船では総員起こしの非常呼集がかかり、切れた曳航索の巻上げとレーダーによるジュビリー号の
監視を続けました。巻上げられた曳航索は2本ともジュビリー号側、曳航索先端のスプライス部分で
切断しており、また、ジュビリー号はアフリカ沿岸を強いベンゲラ海流によって北に流され海岸に打
付けられる心配もあり至急の救助が必要でした。
夜が明ける頃から次第に風波も治まり、非常用曳索(クレモナ・ホーサー 太さ 100ミリ 長さ 200
メートル)の先端をジュビリー号に送るべく「救命索発射器」で細紐の付いたロケットを発射するの
ですが風の影響でロケットは直進せず、なかなかジュビリー号に細紐を渡すことができません。色々
の方法を試みたすえ翌日になってどうにか非常用曳索でジュビリー号を連結することができました。
この曳索切断事故で到着が一週間程も遅れ 41日かかって 6月18日にケープタウンに入港しました。
ケープタウン停泊中は船内で船長、本社工務監督、アメリカから来た石油会社の担当者やイギリス
から来たロイズ保険会社の担当者間で協議が行われ、最終的に曳航索のカティナリー(懸垂曲線)を
大きくするために2本の曳航索を1本に繋ぎ1,600メートルの長さで曳航することが決定されました。
ケープタウンからフリーマントルまでは距離、約4,500マイル。この間は大きな時化もなく 50日か
かって 8月17日、無事にフリーマントルに入港しました。入港数時間前には船首前方に大きな虹が架
かり、虹のトンネルを潜って入港する感じで、本船の入港を歓迎している様で非常に感激したことを
思い出します。ポート・アーサーを 3月25日に出港しフリーマントルに 8月17日に入港しましたので、
この航海は数日の停泊日を含めて 4ヶ月22日の本当に長い航海でした。
この単調な長い航海で船長は技術的な事での心労は勿論ですが、乗組員の船内融和にも大変な心使
いをされた事と思います。船長が乗組員の気晴らしに成ればと暇を見ては作詞したものが、その当時
の私の手帳に記録されておりましたので紹介します。(笑わないで下さい。)
私たち若い乗組員は当直中や仕事の合間に大声でこの詩を替え歌で歌って気分を発散させたもので
した。(替え歌はどう言う歌だったか失念しました。) |