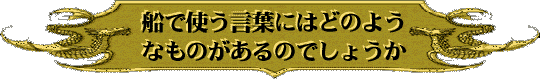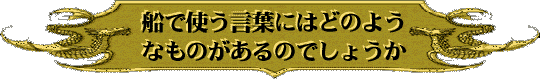|
自 差(Deviation) ----- 1-5 |
磁気コンパスの「南北線」と「磁気子午線」とのなす水平角を「自差」と言います。船内にある
磁気コンパスの自差は、船体構造物の感応磁気やコンパス付近の航海計器、電気配線、その他の鉄
器類により磁力線が乱される事により生じます。また、これらのものの位置関係によって自差は変
化しますので、船首方位を変えると自差もまた変化します。さらに、据付け場所を変えたり、年月
の経過によっても変化します。下のイメージ画は船首方位の変化によって自差が変化する様子を表
したものです。船体中央にコンパス・カードを拡大して描いてあります。
地磁気の磁力線は磁南(+)から出て磁北(ー)に入ります。また、磁石は(+)と(ー)極は引
き寄せ合い、(+)と(+)極、または(ー)と(ー)極は反発し合います。従って、コンパスの
南は青極(ー)で磁南(+)に向き、北は赤極(+)で磁北(ー)を向くことになります。 |
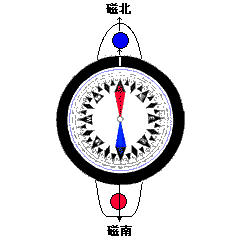 |
ここでイメージ画のように船体感応磁気がコンパスの
据付け位置より船首側が青極(ー)で、船尾側が赤極
(+)の船だとします。船首方位が北の時はコンパス
の指北力は強く自差はありませんが船首方位が北東で
はコンパスの北が船首の感応磁気に引かれ約15度の
偏東自差が発生しています。船首方位が東では感応磁
気はもっと強く作用し約30度の偏東自差が発生して
います。このように船首方位が変われば自差は変化し
ます。また、船首方位が南東、南、南西付近では船体
感応磁気とコンパスの南北の磁針は反発し合いますの
で指北力が弱まり、船体の動揺でコンパスがふらふら
と左右に振れることがあります。自差が大きいと航海
上危険ですので磁気コンパスには自差修正装置があり
一年に一度自差修正を行うことになっています。
自差修正装置は
「磁気コンパスの小部屋」の写真を見
て下さい。 |